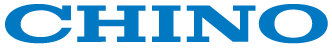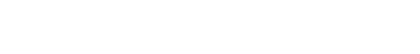基本(温度センサ総論)
接触式と非接触式の違いは?
接触式(熱電対・測温抵抗体など)は対象に触れて温度を測ります。非接触式(放射温度計)は赤外線から表面温度を推定します。応答速度・設置性・対象との熱的結合で使い分けます。
代表的な素子の違い(熱電対/測温抵抗体)
熱電対は起電力、測温抵抗体は抵抗値の変化で温度を検出します。高温・広範囲は熱電対、精度・安定性は測温抵抗体が有利です。
センサの“応答時間”とは?
ステップ的な温度変化に対し、63%(または90%)に達するまでの時間です。感温部を小さく・薄く、熱容量や熱抵抗を下げると速くなります。
使い方(総論)
正しい取り付けのコツ
目的温度に熱的に密着させ、断熱材や熱伝導グリースで周囲の影響を減らします。流体なら流路の中心付近、固体なら代表点へ。
測定器側の設定は?
センサー種別(熱電対種類/測温抵抗体素子・線式)、単位、フィルタ、アラーム、スケーリングを正しく合わせます。
配線(総論)
ノイズ対策の基本
シールド・ツイスト、電源線やインバータから距離を取り、接地は一点アース。長距離は変換器(4–20 mA/IO-Link等)併用が有効です。
延長配線はどう選ぶ?
熱電対は補償導線、測温抵抗体は接続導線の材質・線径でバランス良く。コネクタは極性・接触抵抗を確認します。
環境影響(総論)
振動・湿気・化学雰囲気の影響
振動は断線・接触不良の原因、湿気は絶縁低下、腐食性ガスは被覆劣化を招きます。保護管・端子箱・正しいIPで保護します。
トラブルシューティング(総論)
表示が安定しない/遅い
熱容量不足、応答時間ミスマッチ、フィルタ設定不適、ノイズ混入が疑われます。取り付け見直しと配線ルート整理を。
点検・校正(総論)
現場での簡易点検
氷点/沸点・恒温槽・ドライブロックを用い、基準センサと比較。必要ならスパン/ゼロを調整します。
選定の目安(総論)
熱電対と測温抵抗体、どちらを選ぶ?
範囲・温度(高温は熱電対)、精度・安定(測温抵抗体)、応答(微小は熱電対/薄型測温抵抗体)、環境(耐振動・耐食)で比較。変換器の有無やケーブル長も考慮します。
基本(熱電対)
原理:なぜ電圧が出るの?(ゼーベック効果)
異なる金属を接続し温度差を与えると微小電圧(熱起電力)が発生します。この電圧と基準接点の温度から測温点の温度を算出します(規準熱起電力表)。
種類(K, J, T, E, N, R, S, B)と得意分野
Kは汎用・高温、Tは低温・耐湿、Jは中温、Eは感度高、Nは耐劣化、R/S/Bは白金系で高温炉向き。
接地形/非接地形/露出形の違い
接地形は応答速いがノイズ影響を受けやすい、非接地形はノイズに強い、露出形は最速だが保護性が低い、と覚えます。
使い方(熱電対)
冷接点補償(CJC)って何?
計器端子の温度をセンサで測り、基準0℃に換算する補正です。ロガーやトランスミッタが自動で行うのが一般的です。
熱電対は極性が重要?
逆に接続すると符号が反転します。プラグ/ジャックの記号と色(JIS/IEC)を確認して配線します。
応答を速くするコツ
細径シース、露出・接地形、熱容量を小さく、流体なら流れに直交させるなどで改善します。
配線(熱電対)
補償導線と延長導線の違い
補償導線は近似材、延長導線は同等材で作られます。種類を混在させないのが鉄則です。
シールド/ツイスト/アースの考え方
インバータや高電流から離し、シールドは片側接地。ループを作らない配線で誘導ノイズを減らします。
環境影響(熱電対)
ドリフト・劣化は起きる?
高温や雰囲気で金属が劣化し特性が変化します。定期点検・校正と交換、保護管の選定で抑制します。
トラブルシューティング(熱電対)
値が低めに出る
補償導線や保護管へ熱が逃げると低く出ます。露出長を短く・断熱・熱伝導グリースで改善します。
ノイズでふらつく
接地形→非接地形へ、シールド接地の見直し、入力フィルタや平均化の設定を検討します。
点検・校正(熱電対)
現場チェックの基礎
氷点・沸点・基準温度源で表示器とセットで確認・校正。CJCの健全性も同時に確認します。
選定の目安(熱電対)
タイプと保護管の選び方
温度範囲・雰囲気(酸化/還元/腐食)・応答・耐久で組み合わせます。端子箱/ヘッドレス形、径・長さ、表面状態も合わせて決めます。
基本(測温抵抗体・RTD)
原理:なぜ抵抗が変わる?
金属の電気抵抗は温度で変化します。白金素子(Pt100/JJPT100/Pt1000)が一般的で、再現性・直線性に優れます。
Pt100とPt1000の違い
公称抵抗が100Ω/1000Ω。長配線ではPt1000がリード抵抗の影響を受けにくく有利です。
2線式/3線式/4線式の意味
2線式は最小配線だがリード抵抗の影響大、3線式は工業用の定番(同抵抗で相殺)、4線式は研究・校正用途に最適です。
使い方(測温抵抗体)
自己発熱を抑えるには?
測定電流を必要最小に(例:0.1–1 mA)、連続通電より間欠励起、熱結合を高めて誤差を抑えます。
応答を速くするコツ
薄膜素子・細径シース・スプリング圧接・熱伝導グリースの活用で時定数を短縮します。
配線(測温抵抗体)
3線式は色順・極性に注意?
同色2本+別色1本が基本。端子のA/A’/B表記に合わせ、抵抗バランスが崩れないよう配線します。
長距離での対策
ツイスト・シールド、低抵抗ケーブル、必要に応じてヘッド内に変換器(4–20 mA/デジタル)を置くと安定します。
環境影響(測温抵抗体)
湿気・結露で値が乱れる
絶縁低下やリークで誤差が出ます。防湿構造・樹脂封止・ケーブルグランドで浸入を防止します。
トラブルシューティング(測温抵抗体)
表示が高め/低めにズレる
リード抵抗の補償不良、自己発熱、熱結合不足が主因です。3線式の抵抗バランスと測定電流を確認します。
断線検知・異常検知の設定
トランスミッタのセンサブレーク検知やレンジ外警報を有効にし、上限/下限のフェイルセーフを決めます。
点検・校正(測温抵抗体)
基準抵抗と温度源での確認
基準抵抗器で表示器の入力直線性を確認し、氷点・恒温槽でセンサを実機確認。記録はトレーサブルに残します。
選定の目安(測温抵抗体)
クラスA/B/AAの違いと使い分け
クラスAA>A>Bの順に高精度。必要精度・温度範囲・コストで選び、系全体(センサ+入力器+設置)の不確かさで判断します。
素子形状・保護管・取り付け
薄膜/巻線、シース径、ねじ/フランジ/挿入長、ばね付き圧接など、プロセス条件とメンテ性で選びます。
参考資料(一般公開情報)
- 熱電対の基礎と種類:IEC 60584-1/JIS(タイプ記号・許容差)
- 測温抵抗体の基礎:IEC 60751/JIS(Pt100/Pt1000、クラスA/B等)
- 配線・ノイズ対策:計装配線のガイドライン、各社トランスミッタ取説
- 点検・校正:ドライブロック/恒温槽/基準抵抗器の活用
※ 詳細値や規格の最新情報は、各規格票と製品の取扱説明書をご参照ください。
最終更新日: